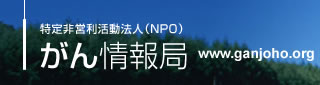- はじめに
- 乳がんの薬物療法
- 薬物療法の目的
- 初期治療は何のため?
- がんの微小転移
- 転移・再発治療は何のため?
- 術後化学療法の有効性
- 術前化学療法の有効性
- 抗がん剤の種類、主な副作用
- ホルモン剤による治療
- 転移した乳がんの治療
- 健康食品・民間療法の考え方
- 抗がん剤治療医の選び方、付き合い方
- 余命を知る事は必要か
1.はじめに
「がん」という病気に共通することは、何らかの原因で体内に発生した癌細胞が、「無秩序、無限」に増え、発生した場所だけにとどまらず、血液やリンパ液の流れに入り込んで他の臓器に流れていく…つまり「転移」するということ。そして、そこでまた無秩序、無限に増えるという性格を持っているということです。また、診断がついて、すぐに初期治療を行なった後、数年、あるいは10年以上たってから、がんが他の臓器に再び発生する…つまり、「再発」をおこすことも、がんの特徴のひとつと言えましょう。全身に散らばっていくことが特徴なわけですから、1か所を切り取る外科手術や、1か所だけに高エネルギーを集中させる放射線治療だけでは、「がん」を制御する事は不十分であると考えられます。病気が全身に及ぶわけですから、全身に効果が及ぶような治療が必要であり、そのためには薬剤による治療が不可欠である、ということです。
「早い時期に見つけたから手術だけで大丈夫、抗癌剤は不要」と考えられていたのは昔の話で、最近では「乳がんの性格によっては早期と考えられても決して手術だけで終わらせてはいけない」「きちんと抗がん剤やホルモン剤による治療をやらなくてはいけない」という考え方が当たり前になってきています。「抗がん剤は副作用が強いから受けたくない」という不安を訴えられる患者さんがいますが、現在は副作用をかなり抑えることができますので、怖がらないでください。ここでは、乳がんの治療として行われる薬物療法(化学療法・ホルモン療法)について解説したいと思います。
2.乳癌の薬物療法
現在、日本にがんの治療薬は90〜100品目あります。このうち、乳がんの治療薬は25-30品目あります。がんのことを「悪性腫瘍」とも呼びますから、がんの薬を「抗悪性腫瘍薬」と呼ぶこともあります。乳がんの治療には、昔から、ホルモン剤が使われてきました。ホルモン剤を使用した治療を、ホルモン療法あるいは内分泌療法と呼びます。抗がん剤は、どちらかというと副作用の強い薬を指しますが、「がんに抵抗する」という意味では、抗悪性腫瘍薬は抗がん剤と同義です。しかし、呼び方にいろいろな方法があってやや混乱することもあるので、ここでは次のような呼び方に統一します。また、化学療法、ホルモン療法、抗体療法、分子標的療法など、薬を用いた治療をまとめて、薬物療法とよびます。
| 化学療法 | 正式には細胞毒性化学療法。やや副作用の強い薬による治療を総称して化学療法と言い、化学療法を行うための薬を抗がん剤と呼びます。 |
|---|---|
| ホルモン療法 | ホルモン療法を行うための薬をホルモン剤と呼びます。 |
| 抗体療法 | ハーセプチン®(一般名トラスツズマブ)を用いた治療です。 |
| 分子標的療法 | がん細胞の無秩序な増殖や転移に関わっている分子の働きを阻害します。現在のところ、グリベック®(一般名メシル酸イマチニブ、慢性骨髄性白血病に使用)やイレッサ®一般名ゲフィチニブ、肺がんに使用)などがありますが、乳がんでは使われていません。 |
3.薬物療法の目的
薬物療法はひとつひとつのがん細胞に作用し、その分裂、増殖を抑えます。以前のがんの治療と言えば手術が第一で、その補助として化学療法やホルモン療法、あるいは放射線治療を行うというふうに考えられていました。この考えの背景には、「手術の時にこぼれ落ちたがん細胞が、乳房の周辺や血液の中に細胞数個の固まりとして残り、それらが他の臓器やリンパ節に移っていき、移った先でまた、分裂、増殖をする」という考え方がありました。
しかしながら、最近のがんの治療では、手術の補助という考え方は陰をひそめつつあります。乳がんでは1980年代以降、「全身疾患」という考え方が提唱されています。「乳房にしこりとして見つかるようになった時には、すでに微小転移が全身に回っている可能性があり、手術や放射線治療などの局所治療よりも全身治療が重要である」という主張が、多くの乳がん治療研究者の間で受け入れられるようになりました。
従って、特にこれから説明する初期治療では、抗がん剤やホルモン剤が大変重要な意味を持つと考えられています。乳がんで抗がん剤治療を行うケースは、大きく分けて2つあります。1つは「初期治療」、もう1つは「転移・再発の治療」です。
4.初期治療は何のため?
初期治療とは、乳がんの診断がついた後最初に行う治療のことで、「化学療法」「ホルモン療法」「手術」「放射線治療」の4つの中から、患者さんの病状に応じて必要なものを選び、最適な順番で治療を行います。患者さんの希望も治療方針を決定する上で重要な要素となりますから、担当医に任せっぱなしにするのではなく、大切なことは治療方針を一緒にご相談いただくことだと思います。
初期治療における化学療法は何を目指して行うのでしょうか。それは「がんを完全に治すこと」です。患者さんによっては「手術+放射線治療」による局所療法だけで十分な場合もあります。しかし、命に関わってくるのはあくまでも転移病巣ですから、微小転移のうちに乳がんを根絶するために、初期治療の段階で全身的な治療である化学療法を行う訳です。化学療法を手術の前に行うか(術前化学療法)、手術の後に行うか(術後化学療法)、という問題は次の「術前化学療法の有効性」のところをお読みください。術後化学療法が必要かどうかを検討する場合には、手術の時の検査結果を参考にします。詳細は、「術後化学療法の有効性」のところをお読みください。
初期治療での抗がん剤治療は、副作用を軽減する手だてを講じながら、決められた期間、決められた投与量と回数の抗がん剤治療をきちんと行うことが必要になります。副作用が強いからといって、薬剤の量や治療回数を減らしてはいけません。
初期治療における化学療法の目的は微小転移の根絶にある、という考え方が正しく理解できていない医師や、抗がん剤治療に不慣れな医師がいます。そのような医師が化学療法を担当する場合、副作用を恐れるあまり、ついつい抗がん剤の投与量を減らしたり、回数を少なくしたりすることがあります。しかし、それでは明らかに「病気の治癒」という目標を達成することができなくなります。
専門医による治療ならば様々な副作用軽減策を講じますから、副作用をほとんど経験せずに治療を終了することができます。抗がん剤を検討する段階になったら、やはり専門医に相談するほうがいいでしょう。
ホルモン受容体が陽性の場合には、手術や化学療法が終わった後、ホルモン療法が必要になります。初期治療におけるホルモン療法は、最近では5年から10年間と、大変長い期間使用するようになってきました。詳しくは、「初期治療におけるホルモン療法」を参考にして下さい。
ホルモン療法を行うにあたって気をつけるべき点として、「化学療法とホルモン療法を同時に行わない」ということがあります。初期治療では、抗がん剤の点滴や服用をしているうちにホルモン剤を併用すれば、治療効果が損なわれることが示されています。
5.がんの微小転移
がん細胞ができることを発がん、細胞ひとつがふたつ、ふたつがよっつ、よっつが八つと増えていくことを分裂あるいは増殖、そして遠くの臓器に移ることを転移、あるいは遠隔転移と呼びます。最初にがんができたところを原発病巣(原発巣)、転移したところを転移病巣(転移巣)と呼びます。転移は、血液やリンパの流れにのって、最初のうちはおそらくがん細胞1個〜数個程度のまとまりとして、他の臓器に移って起こるのだろうと考えられています。この段階では、どんな敏感な検査をしても転移を見つけることはできません。そのような状態を目に見えないほど小さい、という意味から微小転移と呼びます。
微小転移は、ちょうどタンポポの種が、風に吹かれて遠くの土地まで飛んでいって着地した状態にたとえられます。つまり、春になって芽が出て花が咲くまでは、そこに種があることはだれもわからないように、微小転移が分裂、増殖し、ある程度の大きさになって…例えば、肺転移が胸部レントゲン写真に写るぐらいの大きさになって初めて、「転移した」ということがわかるのです。この状態を転移性乳がんと呼びます。だからこそ、薬による全身の治療が必要となるのです。
6.転移・再発治療は何のため?
遠隔転移を来した場合、その状態からの完全治癒はかなり難しく、通常3-5%程度といわれています。「そういえば遠隔転移してから10年以上にわたり、病気が再びぶりかえして来ないな」という患者もいますが、そういう人はきわめて少ないのです。大半の患者さんに対しては、「病気の進行を遅らせ、症状を和らげる」ことが治療の目的となります。QOLの観点からも「穏やかな治療」を選ぶことが重要なのです。
7.術後化学療法の有効性
乳がんの手術をした後、外科の先生から「手術で取り切れました」と言われても、「脇の下のリンパに転移はありませんでした」と言われても、手術後数年、あるいは十年以上経ってからも、遠隔転移が現れる方がいます。遠隔転移は、微小転移が原因と考えられています。手術直後に「微小転移を根絶してしまおう」という目的でおこなわれるのが術後化学療法です。術後ですから原発病巣はすでに切除されていますし、微小転移といってもどこにあるのか姿は見えませんし、特に症状もない。しかし、化学療法による副作用はでる。こんな状態で12週間から24週間にわたって化学療法をうけるためには、よっぽど効果について正しい認識を持っていないと続けられるものではありません。
では、「効果」とはなんでしょうか。術後化学療法を受けている患者さんに、「今の治療に効果はあるのでしょうか?」と尋ねられることが時々あります。正直な答えは「わかりません」ということです。なぜ、分からないのかというと、術後化学療法の効果は、「手術だけの場合と、手術のあとで化学療法を行った場合とを、数百人〜数千人の患者を対象に比較した臨床試験の結果、再発、あるいは死亡した患者が○○%減少した」というデータが元になっているからです。
我々は、「あなたと同じような病状の患者さんが、手術を終わってから一定期間化学療法を受けた場合、再発のリスクを○○(たとえば3/4)に減少することはできる」ということは患者に説明できても、一人一人の患者について効いているか?と、いうことは全くわからないのです。手術だけ、あるいは手術と放射線治療というような局所治療だけですませた場合に再発する患者の割合…これをベースラインリスクと呼びます。ベースラインリスクを知るには、次のような検査の結果を参考にします。
- 手術で切除した腋窩リンパ節の病理学的検査で腋窩リンパ節に転移があったか、あった場合はいくつあったのか
- ホルモン受容体(エストロゲン受容体(ER),プロゲステロン受容体(PR))は陽性か陰性か。
- 病理学的に調べたがんの大きさ(腫瘍浸潤径)はどれぐらいか。 細胞の顔つき、といわれるグレードはどうか。
これらの検査を「予後因子」と呼びます。また、最近では、HER2(ハートゥと読みます)の状態も、再発のリスクを推定する根拠としよう、ということになりました。
たとえば60才女性、腋窩リンパ節転移陰性、ホルモン受容体陰性、病理学的腫瘍浸潤径2.5cm、グレード3であった場合、手術後10年以内に再発する割合(ベースラインリスク)は45%と考えられます。
つまり、おなじような病状の患者さんが、400人いたとすると、10年以内に、400かける0.45、180人が再発することになります。しかし、再発する患者と再発しない患者は、抗がん剤を検討する時点では見分けることができませんから、ある程度のベースラインリスクのある患者は抗がん剤治療を受ける方がよい、と説明されます。400人全員がEC(エピルビシン、シクロフォスファミド)という抗がん剤治療を受けたとすると、ECによる再発抑制(再発が免れる)効果は、計算上56人ということになります。この再発を免れる患者の割合が、治療によるリスク抑制効果というわけです。
手術、抗がん剤治療をうけた患者は10年経ってみると、3種類に分けることができます。手術だけで乳がんが治っていた患者、この人たちにとってみると術後の抗がん剤は不要だったといえます。つぎに、手術の後、抗がん剤をしても再発した患者です。この人たちは、抗がん剤も、ひょっとしたら手術も意味がなかったのかもしれません。抗がん剤治療をうけて、あきらかに良かったと言える人が残りの人たちです。ただ、結果的に再発した患者でも抗がん剤をしなければ、もっと早く再発していたのを再発までの期間を延ばすことができた、という効果はあるかもしれません。まだまだ分かっている事は不完全です。
抗がん剤治療による副作用、病院に通ったり入院したりという不便、経済的なコストなど、治療を受ける立場の患者にとっての、様々な害悪を「ハーム」と呼びます。
術後抗がん剤治療を受けるかどうかを検討する場合には、上記の「ベースラインリスク」、「抗がん剤によるリスク抑制効果」、そして「ハーム」についてのバランスを十分な情報に基づいて決めなければなりません。抗癌剤治療を受けるか受けないか、これを決めるのはなかなか難しい問題です。いろいろ副作用がでても、それらはすべて抗癌剤治療が終われば消失してしまいますが、再発の恐怖や不安はずっと続きます。決して、抗がん剤治療をやれば再発のリスクがゼロになるわけではありませんが、できるときにできることをやっておけば、後々になってできることはやったのだから、という気持ちが自分を安心させると言うこともあるでしょう。
8.術前化学療法の有効性
化学療法を手術の前に行う方法を「術前化学療法」と呼び、最近、行われる機会が増えてきています。乳がんと診断された患者にとっての重大な関心事は、乳房を全部取らなければいけないのか、温存手術ができるか、ということだと思います。
日本乳癌学会で出している「乳房温存術のガイドライン」によると、温存術ができる患者さんは、しこりの大きさが3cm以下、広範な石灰化(マンモグラフィーで広い範囲に石灰化があるということ)がない、腫瘍が1個である、というような条件を満たす場合とされています。しこりが大きい場合や、しこりが乳頭に近いところにある場合、乳房温存術ができない、といわれることがあります。このような患者さんにとって術前化学療法は朗報です。
術前化学療法とは、まず抗がん剤治療を行い、腫瘍を小さくしてから乳房温存術を行う方法です。乳房を全部取る手術のほうが温存術よりもすぐれている、安心である、ということはありませんし、一日でも早く手術をしなければ、その間に遠隔転移が進んでしまうということもありません。むしろ、生命に関わる遠隔微小転移に対して、先に治療を行うわけですから、手術のために歳月を費やすよりはずっと安心、という考え方もあります。
術前化学療法は1980年代から、「局所進行乳がん」の患者を対象に行われてきました。局所進行乳がんとは、乳がんと診断された時点でがんが皮膚表面に露出している、胸の筋肉や肋骨など胸壁まで達している、あるいは脇の下のリンパ節への転移によって腕がむくんでいる、などの病状を指します。このような局所進行乳がんは「手術不能」と呼ばれ、すぐには手術をしないでまず抗がん剤で幾分でも小さくしておいてから手術をする、という方法がとられます。
最近では放射線治療技術も進歩しているので、手術のかわりに放射線治療を行う場合もあります。
1990年代に術後化学療法と術前化学療法を比較する試験が行われた結果、術前化学療法の再発抑制率は術後化学療法と同じであり、さらに、乳房温存術を実施できる患者の割合が明らかにふえたのです。
それでは、術前と術後、どちらの化学療法がより効果があるのでしょうか。治療の目的は、どちらも全身に散らばっている可能性のある微小転移を根絶することです。抗がん剤治療の期間は、術前、術後のいずれも12〜24週間。抗がん剤治療に伴う副作用は、同じように現れます。
しかし、術前化学療法の場合、約8割〜9割の患者さんでは、しこりが小さくなっていくという化学療法の効果を患者自身も体験できますから、「こんなに効いているのなら多少の副作用は我慢しよう」と前向きな姿勢になることができます。
一方、術後に化学療法を行う場合、臨床試験で確認された効果の程度は頭で理解できているものの、患者一人一人にとって、「私は効いているの?」ということに皆目検討がつきません。効果は体験できず、副作用は体験するとなれば、よほど効果に関して理屈で理解できていないと、長丁場の化学療法を続けられるものではありません。副作用があるからといって、途中で治療を止めてしまったり抗がん剤の分量を減らしてしまったりしては、目指すべき効果が得られないわけです。
また、化学療法はあくまで全身療法ですから、これをやれば放射線照射をしないで済む、ということはなく、温存術を行ったら局所療法として放射線治療を加えないといけないことになります。
このように、術前と術後の化学療法を比べてみると、どうも術前化学療法のほうが良さそうです。
9.抗がん剤の種類、主な副作用
術前化学療法でも術後化学療法でも一剤のみの抗がん剤を使うことはなく、多剤併用といって、作用の異なる抗がん剤を2-3種類併せて使用します。同時に併用することもありますが、最近では順次投与と言って、2種類のレジメン(治療のひとまとまりをレジメンと呼びます)を12週間ずつ、順番に投与する方法が用いられることが多くなっています。どの組み合わせでいくかは、患者さん一人一人違いますので担当医と話し合って下さい。
よく「抗がん剤の治療で命を縮める可能性があるのでは」と心配する人がいます。しかし、「抗がん剤が延命につながることはあっても、命を縮めることはありえない」これだけは間違いないことです。どのような副作用が出るか、代表的なものをいくつかご説明します。
| 吐き気・嘔吐 | 吐き気や嘔吐は、ほぼ薬でコントロールできます。強い吐き気を伴う抗がん剤には、ブリプラチン®、ランダ®など(一般名:シスプラチン)やアドリアシン®(一般名:塩酸ドキソルビシン/アドリアマイシン)、ファルモルビシン®(一般名:エピルビシン)などがあります。 |
|---|---|
| 神経毒性 | タキソール®(一般名:パクリタキセル)などで出現しますが、今のところ十分なコントロール方法はありません。しかし、治療終了後3〜6か月ぐらいで副作用は完全になくなるので、治療中は辛抱していただきたいものです。 |
| 口内炎 | 5-FU®(一般名:フルオロウラシル)を使った場合に出ることがあります。 |
| 全身倦怠 | タキソテール®(一般名:ドセタキセル)を使った場合、3割ぐらいの患者さんに出ると言われています。今のところ、この副作用を防ぐ良い薬はありません。抗がん剤の副作用だと思っていたら、実は、ビタミン不足や睡眠不足が全身倦怠を引き起こしていた、という場合もあるので原因をはっきり見極めることが大切です。 |
| アレルギーによる過敏性反応 | 副作用の中でも一番注意が必要です。タキソールやタキソテールを使った場合、約3パーセントの患者さんに重篤なアレルギー反応が出るので、投与に当たっては細心の注意を払うことが必要です。 |
| 血管に対するダメージ | 点滴が血管の外に漏れてしまって、点滴しているところが腫れてしまうような場合、薬剤によってはその部分に潰瘍ができてしまったり、ひどい場合には皮膚移植が必要となったりします。
|
| 好中球減少 | 「抗がん剤治療をすると免疫力が落ちる」などと言う人が多いです。大部分の抗がん剤では、点滴後7日から12日目あたりに、白血球の成分である好中球が減少します。この時期は、細菌感染に対するからだの防御力、すなわち免疫力が低下します。その時期には38度を超える熱が出ることがあります。しかし、15日目を過ぎれば細菌感染に対する免疫力は元通りに復活しますから、21日を過ぎたあたりに、また、次の抗がん剤の点滴を安全に行うことができるわけです。 |
| 脱毛 | 女性にとっては深刻な問題です。アンソラサイクリン系薬剤、タキサン系薬剤において脱毛は必発です。最初の点滴開始の15〜16日目頃から抜け始め、ほとんどの毛髪が抜けます。しかし、点滴が終了するころには発毛が始まります。大切なことは、抗がん剤の種類によって現れる副作用が異なりますから、「どの薬で、いつ頃、どんな副作用が出るか、そしてそれはいつ頃回復するのか」を正しく把握し、あらかじめ準備できることは準備しておくことです。 |
10.ホルモン剤による治療
初期治療においては、手術と化学療法(抗がん剤治療)が終了した後にホルモン療法をどうするか考えるのが普通です。ホルモン受容体の検査結果や腋の下のリンパ節転移の数などを考慮して、方針を考えます。
ホルモン受容体というのは、がん細胞の中に女性ホルモンとくっつくカギ穴、受け皿のことです。乳がんの場合には、原発巣にしても転移巣にしても、ホルモン受容体を測定することによって、ホルモン剤が効くタイプか効かないタイプか分かります。
ホルモン受容体には、「エストロジェン受容体」と「プロゲステロン受容体」の2つがあります。いずれか陽性の場合には、ホルモン療法の効果が期待できるわけです。陰性の方の場合は、全然効きません。陰性でも「念のためやっておきましょう」と勧める病院もありますが、陰性ならばホルモン剤は使ってはいけないのです。手術をしてから1か月以内ぐらいにホルモン受容体が陰性か陽性かを必ず確認をしないといけません。
| 閉経前の場合 | ある程度微小転移・再発の恐れがありますので、閉経前でホルモン受容体が陽性の方は、まず術後に抗がん剤ではなく、ホルモン剤のゾラデックス(一般名:酢酸ゴセレリン)という卵巣機能を抑える注射を行います。女性ホルモンをエサに増殖するがん細胞の働きをブロックし、微小転移を抑制するためです。
|
|---|---|
| 閉経後の場合 | 閉経後の方にはホルモン受容体が陽性でも、まず抗がん剤治療を行います。術前でもいいのですが、術後の場合は12〜24週間行います。それが終わった後、ホルモン療法を少なくとも5年間やります。ホルモン療法は、術前に行うことはありません。
|
11.転移した乳がんの治療
転移性乳がんでは、前も書きましたが症状を和らげる、QOL(生活の質を高める)を損なわないようなるべく穏やかな治療を行います。
転移しやすい場所
がんが同じ場所に出るのが「局所再発」で、違う臓器に移ることを「転移」と言います。転移しやすい臓器としては、肺、骨、胸膜(がん性胸膜炎)、肝臓、皮膚、脳、体表リンパ節などが多く、眼底、副腎、後腹膜リンパ節、腹膜(がん性腹膜炎)などがあります。| 肺転移 | 直径数cmの結節を形成するもの、気管支、血管、肺胞周囲の間質に浸潤するものがあります。後者の病型は「リンパ管性肺転移」と呼び、肺のコンプライアンスの低下、肺胞レベルでのガス交換障害を起こすため、呼吸困難を起こしやすいです。 |
|---|---|
| 骨転移 | 腰椎、胸椎、頸椎、骨盤、胸骨、大腿骨、上腕骨、肋骨など、赤色骨髄のある体幹近くに出現し、通常は骨がもろくなり、重みが加わる部位(脊椎、大腿骨)の骨折、疼痛、高カルシウム血症が起こります。 |
| 肝転移 | 広範に及ぶこともありますが、多くは数cm大の結節性転移です。広範に及ぶ場合は、肝実質障害、合成能障害、排泄機能の障害などを伴います。 |
| 脳転移 | 神経症状、脳圧亢進症状がなければ積極的に画像診断で調べる必要はありません。リンパ管性肺転移、広範な肝転移、脳圧亢進症状を伴った脳転移は、生命予後を脅かす可能性があります。 |
上手に付き合うことがコツ
初期治療後、どれぐらいの患者さんが転移・再発するかと言いますと、10年以内にだいたい3割〜4割と言われています。ただし10年、15年、20年経っても転移・再発することがあります。これが乳がんの一つの特徴と言えます。
乳がんが転移・再発した場合、「治る」ということはないのです。ですから、「慢性疾患」として上手に付き合っていただきたいと思います。例えば高血圧や糖尿病をお考えください。一生薬を飲んで、食事療法や運動療法が必要になったりしますね。そういう心構えが大切だと思います。
微小転移は、いくら早く診断してもなんの意味もありません。例えば最近はやりのPET検査では、確かに早い時期に診断することができます。しかし、それから数か月経ったレントゲン写真などで分かる段階になってから治療を開始しても、結果的には同じことです。症状もないうちから治療は必ずしも必要にはならないのです。
また、「抗がん剤治療の最中に腫瘍マーカーが変化した時には、治療方法を変えたほうがいいのでしょうか?」と不安になられる患者さんがいます。腫瘍マーカーの結果はそれほど確実なものではないですし、この検査自体、単なるきっかけでしかありません。したがって、腫瘍マーカーが上がったからといって、あわてて抗がん剤を変える必要はないでしょう。腫瘍マーカーが変化した場合は、CT、MRIなどの画像検査を行うのが普通です。もし、がんの増悪が発生した場合は、腫瘍マーカーが変化してから2〜3か月以内に、画像診断で転移の増悪や新しい転移の出現をとらえることができます。遠隔転移の治療の目標は、あくまで痛みや呼吸困難などの症状を和らげることですから、遠隔転移が画像検査で確認された時点で、症状があれば、治療方法を変えたほうがいいでしょう。
今使用している治療の効果を正しく見極めることが大切で、腫瘍マーカーの変動だけで治療を変えてしまうと、せっかく効き始めた治療を変えてしまうことになりかねません。
治療に関する原則
全身疾患ですから、可能な限り全身治療を選択します。原発部位、皮膚転移などで、痛み、感染、出血など、局所コントロールが必要な場合は手術、放射線照射などの局所治療を追加します。脳圧亢進症状を伴う脳転移に対しては放射線照射を行います。重みの加わる部位で骨折の危険がある場合や骨折を起こした場合、痛みを伴う場合は、骨転移に対する局所治療を行います。これら以外の局所治療は、原則として、診断確定、ホルモン受容体・HER2などの検査を目的とする以外は治療としての意味はありません。
抗がん剤とホルモン剤では、転移部位による効果の違いはありません。ホルモン感受性のある方では副作用も軽いので、まずホルモン療法から開始します。ノルバデックス®(タモキシフェン)をずっと飲んでいたような場合には、1年以内に第二次ホルモン療法にいきます。手術後に使っておらず、閉経前の方の場合には、ゾラデックス+ノルバデックスという選択肢があります。ゾラデックスだけで40歳前から10年以上治療している人がいますし、肺にポツポツと転移が出ていた人で、リュープリンでずっと治療していた人が、途中で薬を止めても転移が消えてしまった人もいます。閉経後の方の場合はアロマターゼ阻害剤またはノルバデックスを使います。ホルモン剤を可能な限り3種類ぐらい使います。ホルモン療法が無効の場合には、抗がん剤を使用します。HER2陽性(HER2タンパク3+、またはFISH +)の場合は、可能な限り早い時点からハーセプチンを使います。なお、抗がん剤とホルモン剤は同時期に併用しません。
話題のハーセプチン(抗体療法)
ハーセプチン(一般名トラスツズマブ)は1990年代の初めから開発が始められたモノクローナル抗体です。このハーセプチンを用いた治療を抗体療法と呼びます。乳がんの患者さんの2割前後は、がん細胞の表面に「HER2」と呼ばれるタンパクが過剰に出ています。これはアンテナのようなもので、細胞膜を貫通するような形で細胞の内と外にあり、がん細胞の増殖に必要な物質を細胞の外から内に取り込むような働きをしています。
このHER2に対しての、クローンを1本にした(モノクローナル)抗体がハーセプチンで、手錠のようなものです。ハーセプチンが、がん細胞が生きていくために必要なエサを取込もうとするHER2タンパクの働きを妨げることでがんが死ぬ、という仕組みです。
ハーセプチンが効くタイプかどうかは、免疫染色(免疫組織化学染色法)を行い、乳がん細胞を染めます。染まり方を0、1+、2+、3+の4段階に評価し、+の数が多いほど強陽性となります。3+の方は文句なくハーセプチン治療の対象になり、4割〜5割の方には効果が出ます。2+という方が問題で、効果が出るのは1割ぐらい。そこで2+の方は、もう一つの検査、フィッシュ(FISH:Fluoresent insite hybridaization)法を行います。これはHER2をコードしている17番目のDNAを光らせ、たくさん光るほど陽性でハーセプチン治療の対象になります。HER2が陽性の人は、まずハーセプチン単独での治療を始めます。
ハーセプチンは一週間に1回の点滴になります。副作用として、38度近く熱の出ることがあります。しかしその副作用は1回目の点滴で4割の患者さんに出ますが、2回目以降は出ません。ハーセプチン単独で効果がない場合には、ハーセプチン+タキソールとか、ハーセプチン+ナベルビン(酒石酸ビノレルビン)といった抗がん剤との併用を行うことになります。
12.健康食品・民間療法の考え方
民間療法についてお話をしたいと思います。がんの告知は、以前に比べれば、かなり一般的になってきました。しかし治療に関して、患者さんに十分満足の行く説明がなされているかというと、そうではないことが多いです。また、抗がん剤治療もホルモン剤治療も万能ではありません。そうすると患者さんは代替医療に頼りたくなってきます。家族や親族一同も「あれを飲んだら」「これがいい」と持ってきてくれることがよくあります。その中で一番多いのがアガリクス、メシマコブ、サメの軟骨、プロポリス、カニの甲羅、キチンキトサン、DHAC…。これらは健康食品と呼ばれています。
ところが、効果も安全性も確認されていない、というのが現実です。これはとても危険なことです。つい最近、アガリクスで劇症型肝炎を起こして亡くなった男性の記事が新聞に載りました。患者さんは担当医に言わずに飲んでいる場合が多いですし、言ったとしても、医師のほうも「気休め程度ならまぁいいんじゃないですか」ということになる。ところが、劇症型肝炎で亡くなった患者さんもいるのです。安全性も効果もまったく証明されていませんし、お金もかかります。すべての健康食品は不健康食品である、と言っても過言ではありません。
13.抗がん剤治療医の選び方、付き合い方
腫瘍内科医は抗がん剤治療の専門家ですから、抗がん剤を使って最大の効果を引き出し、最小の副作用にとどめることができます。しかし、腫瘍内科医は、人手不足です。乳がんを診る腫瘍内科医は全国でも20人程度とまだまだ少ない。そこでお薦めしたいのは、乳がん治療を外科医の立場で専門的に取り組んでいる病院を探すことです。外科医と乳腺外科医は、専門医の認定方法もまったく別です。乳腺科、あるいは乳腺外科と標榜している病院や、「乳がんの手術件数が多い病院」がその目安になります。乳がんの手術件数が多い病院では、手術だけでなく抗がん剤治療にも実績がありますし、副作用の対策もうまくできます。手術件数は年間100例が目安で、10〜20例しかないような医療施設では、抗がん剤治療は受けないほうがいいでしょう。
「ここの病院では、年間に何人ぐらいの患者さんが乳がんの手術を受けていますか」と質問してみて、手術件数が少ないようなら地域の他の専門病院に移ったほうがいいと思います。乳がん患者をサポートするなどの患者会に照会すると専門病院を探してくれます。また、乳がんの専門家だからといって、医師同士、完全に意見が一致することはありません。例えば、乳房温存手術にするか乳房全摘手術にするか、抗がん剤が必要かどうかといった問題については、意見が分かれることがあります。では、治療法について複数の医師から違う意見を聞いたときに、何を規準に判断すればいいか。ここで気をつけたいのは、医師が「自分にとって好ましい治療法を提示してくれたかどうか」を判断の基準にするべきではない、ということです。
例えば、医学的に見て抗がん剤治療が必要なのに、「抗がん剤は絶対にいやだ」という患者さんがいるとします。この患者さんに対して、A医師は抗がん剤が必要だと言い、B医師は、抗がん剤は不要だと言う。この場合、患者さん自身が抗がん剤治療を望まないからB医師を選ぶ、というのは正しい選択とは思えません。
医師には、患者さんの好みや希望を聞いた上で、「医学的には抗がん剤治療が必要ですが、あなたがこれだけのリスクを覚悟の上で抗がん剤をやらないというのなら、他の手もありますよ」と、患者さんの納得がいくような説明をする義務があります。それを聞いた上で、抗がん剤を使わないことを選ぶかどうかは、最終的には患者さん本人の選択です。しかし、さらに一歩進めて、「B医師は、手術は乳房温存でいいという意見で、先生は全摘が必要だとおっしゃいますが、その意見の違いはどこからくるのですか」と聞いてみる。そうすれば、A医師は「私は、こういう理由で乳房切除が必要だと思っています」と答えるでしょう。このように、患者さんの側から医師に働きかけ、納得のいく説明を求める努力をすることも必要だと思うのです。
14.余命を知る事は必要か
厳しい状況になったときに、「もう○カ月の命です」と医師に言われ、動揺する患者さんが増えています。「余命○カ月」というのはあくまで平均値、あるいは中央値であり、残された寿命を正確に予測することは専門家にも不可能だと思います。例えば、ある病院で治療を受けた患者さん100人の再発後、死亡までの期間の中央値は30か月というデータがあるとします。半分の患者さんは、30か月以内に亡くなった、半分の患者さんは、30か月以上、生存したというのが事実ですが、なかには再発後、10年、20年と生きておられるケースもあり、一概に断定することはできません。
よく「半年前に余命30か月と言われたので、自分に残された時間は、30−6=24か月」という緻密な方がいますが、これはほとんど意味をなさないと思います。患者さんの中には、「自分が経営する会社の仕事を整理する必要があるので、余命を知りたい」という人がいるのも事実です。しかし、患者さんが求めてもいないのに余命告知をする医師がいるとすれば、それは、その医師の情報提供スキルが未熟だというほかありません。いずれにしても、余命○カ月という数字はあまり当てにならないので、ショックを受けて落ち込むことのないようにしていただきたいものです。むしろ「余命は自分で決める」位の心意気が必要な時もあります。
大切なことは、一日、一日、楽しく、充実した毎日を過ごす、ということでしょう。その積み重ねとして、気づいたら10年、20年という歳月が流れていた、ということもあるでしょう。