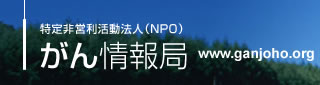渡辺 亨
国際医療福祉大学臨床医学研究センター
教授 山王メディカルプラザオンコロジーセンター長
私は腫瘍内科医として国立がんセンターで16年間勤務した。この間、抗がん剤、ホルモン剤、抗体など、新薬開発の治験や研究者主導による臨床試験、乳がん患者の治療、およびレジデントや研修医の教育、そして地方講演などの情報提供活動に従事してきた。これらの経験を通じ、我が国では、がん診療拠点が決定的に不足しているという現状を強く認識した。自らの人生の転機を迎えたこともあり、辻々の交番のような街のがん診療施設の設立をめざし、2003年9月、東京都心の診療所に「オンコロジーセンター」を開設した。オンコロジー(oncology)とは腫瘍学、すなわち「がん医学」であり、ここでは、外来化学療法とセカンドオピニオン提供を主な診療内容としている。世間では、抗がん剤治療を専門とする腫瘍内科医が不足し、十分な抗癌剤治療を受けることのできない患者が多い、この現状をどうにかしなくてはと、マスコミでもしきりに取り上げられている。確かに、現在の抗がん剤治療には問題が多い。どのような問題なのか? どうすれば、その問題を解決できるのか? 我が国のがん医療に求められていることは何か、について考えてみたい。
広がらないセカンドオピニオン
2003年9月の開設から1年間に、セカンドオピニオンを求めて236名の患者あるいは家族がオンコロジーセンターを訪れた。このうち、現在の担当医からの紹介状を持参した患者は全体の三分の一にあたる79名、三分の二は、担当医には告げず、あるいは担当医の了解を得ないで、受診したことになる。患者の大部分は、担当医の説明を十分に理解しており、詳細な経過を自分の言葉で説明できるので、紹介状がなくてもセカンドオピニオンを提供することはできる。しかし、抗がん剤治療であれば、使用薬剤名、投与量、などを正確に記載した担当医からの紹介状があるに超したことはない。患者の立場に立つと、担当医にセカンドオピニオンを聞きに行くので紹介状を書いてほしい、とは切り出しにくい。ある大学教授が、「セカンドオピニオンとは、現在、診療をうけている医師、病院を見限って、他の病院にいくこと」と学会ので公言していたが、これは違う。セカンドオピニオンとは、「現在受けている治療やこれからの治療を安心して受けるために担当医師以外の専門家の意見を求めること」である。今かかっている医療機関での医療内容をさらによくするためにセカンドオピニオンが機能してほしい。しかし、現状では、「俺の治療を信用できないのか」、というような意識が医師側にあり、患者側にも、「今までお世話になったのに申し訳ない」、というような意識が働いていることも否めない。セカンドオピニオンが普及定着し、紹介する側も、紹介される側も、ややこしい感情的もつれを伴わない対応ができるようになることを願う。
セカンドオピニオンが普及しない理由は他にもある。医療費である。現在の保険診療では「セカンドオピニオン」という項目はない。診療情報提供料として220-520点(診療報酬額はその10倍)が認められているが、これはあくまで、医療機関から医療機関への情報提供であって、医療機関から患者への情報提供では、初診料250ー270点だけである。これでは、セカンドオピニオン外来を設置する経費すら捻出できない。セカンドオピニオンは、必要不可欠な医療行為ではないので、時間とお金に余裕のある患者が私費でまかなう、という自由診療の考え方もあるが、このあたりの議論が十分になされていないようである。
不十分な治療選択
セカンドオピニオンを求めて来院した患者の治療内容をみると、治療方法の選択が不適切と思われる場合が多い。がんの治療には大きく分けて、外科手術、放射線照射、薬物療法がある。薬物療法はさらに、抗がん剤、ホルモン剤、抗体製剤、サイトカイン製剤に分類される。外科手術、放射線照射は、がん細胞が腫瘤を形成している部位だけを対象とする治療であるので局所療法と呼ぶ。一方、薬物療法は、全身くまなく効果が及ぶため全身療法と呼ぶ。肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、卵巣がんなどの固形がんは、原発臓器で発生し、細胞分裂を繰り返し増殖し、腫瘤の直径が1-2cmになると、レントゲン写真や、体表から触ってもわかるようになる。この状態を放っておくと、他の臓器に転移するので、早めに見つけて早めに手術しましょう、というのが早期発見、早期手術の考え方である。ところが、他臓器への転移は、実はもっと早い時期、すなわち原発臓器での腫瘤形成と並行して起きている可能性がある、という考え方が乳がんなどで主流となってきた。全身にタンポポの種のように、目には見えないけれども転移が散布されている場合がある、という全身疾患の考え方である。米国では1980年代後半に、「乳がんの初期治療の一環としての抗がん剤、ホルモン剤などの全身治療の重要性」に関する注意喚起が国立がん研究所から出されている。ところが、我が国では、乳がんと診断された患者の99%は外科医師だけにより、治療方針が決定されるため、どうしても手術に重きが置かれざるを得ない。また、専門的なトレーニングを受けていない場合、抗がん剤治療に伴う適切な副作用マネージメントができないという技術的な問題もある。例えば、抗がん剤に伴う悪心・嘔吐を例にとれば、十分な副作用対策を講じた場合、つわり程度のむかむかはあっても嘔吐することはない、という患者が大部分だ。仕事の行き帰りに、抗がん剤点滴を受けている患者も多い。
初期治療の目的は、治癒をめざすことであり、そのためには副作用対策を十分に講じ、有効な治療を併用しなくてはならない。
一方、初期治療後、明らかな遠隔転移、再発病巣が出現した場合、その時点から治癒を達成することは困難な場合が多い。治療の目標は、痛みを和らげるなどの症状の緩和や、仕事や社会活動などの社会生活や、趣味や日常生活を充実させるなどの、QOL(クオリティオブライフ、生活の質)を高めることになる。その為には、なるべく副作用の少ない治療を優先させたり、症状緩和策を十分に行なうことなどが重要となる。決して、この時点で、大量の抗がん剤や、負担の大きい手術を行なうことは、患者にとって、いいことはひとつもない。
「目に見えるものは切りましたという詭弁」と「てんこ盛り治療」
遠隔転移を来した場合、外科手術はあまり役立たない。腹腔内に広く拡がった胃がんの転移病巣に対して、外科手術を敢行し「目に見えるものは全部とりました」という説明が、いかにむなしいものか、は、数年前、がん告知で話題をまいた芸能人のケースでも実証ずみであろう。確かに、胃がんは、固形がんのなかでは、比較的、抗がん剤が効きにくい。もし、上記の外科医の対応を腫瘍内科医が「無意味な手術ではないか」、とコメントしたとすると、「抗癌剤では見えるものすら消せないだろう。」というような反論が予想できる。しかし、この反論には、治療をうける側の患者の視点が完全に欠落している。内科医対外科医の対立軸ではない。患者は、意味のある治療を希望しているのである。
一方、抗がん剤やホルモン剤などの薬物療法が進歩したといっても、遠隔転移を伴った状態では、若年男性の睾丸腫瘍や、分娩後の絨毛癌など、極めて感受性の高い一部の疾患以外ではなかなか治癒をさせることは難しいのが現状である。遠隔転移を来した場合、治療目的は、クオリティオブライフ(生活の質)の向上であり、延命である。しかし、遠隔転移を来した患者の治療で、しばしば遭遇するのは、効果のあると思われる治療薬剤をすべてまとめて投与する、てんこ盛り治療である。これでは、何が効いていて、何が効いていないのか、が全くわからなくなってしまう。特に転移性乳がんでは、3-4種類のホルモン剤、4-6種類の抗がん剤が有効であり、これらを如何に効果的に使用していくか、ということが、質の高い延命につながることは検証済みである。
グループ診療、チーム医療
国立がんセンター病院には、第14期レジデントとして昭和57年6月1日からお世話になった。レジデント(住み込み研修医)の字義どおり、病院内に住み込み、昼夜の別なく入院患者の診療、外来診療の見学・補助、症例カンファレンス、英文抄読会、院内発表や地方学会での準備、など、多忙な日々を過ごした。私の指導者は阿部薫先生(国立がんセンター名誉総長、現在、横浜労災病院長)で、当時、阿部先生の診療グループは「内分泌グループ」と称しており、緩やかなグループ診療制をとっていた。グループ診療とは数名の医師が、診療方針について等しく智恵を出し会い、合議を形成しながら診療を進めていく形態である。主治医制では、主治医以外の医師は、診療方針や、治療内容の最終決定には関与しないのが普通である。「おれの患者、私の先生」という強固な人間関係を好む場合には、グループ診療制よりも、主治医制の方がいいのかも知れない。しかし、がん治療の場合、治療方法の選択については、必ずしも正解が一つとは限らない。いくつかの選択肢の中から、その時々で、最も適切と思われるものを選ぶ過程が必ずある。また、がんに伴う症状や、治療に伴う副作用を正しく把握するためには、薬学的知識や、病態生理を正しい理解が不可欠であり、複数の専門家の経験知の集結が必要である。患者からみると、グループ診療は、担当の医師がころころ代る、主治医不在という印象を持たれることがあるが、そうではなくって、複数の目で見て、複数の頭で考えることのメリットは大きいと思う。
チーム医療も、がん医療ではとりわけ重要である。内科医、外科医、放射線治療医、看護師、薬剤師、などの、専門の異なった医療職が、協調して、治療を進めるのがチーム医療だ。手術後、いつから、食事を開始するか、リハビリをどうするか、抗がん剤治療の副作用対策をどうするか、など、複数の医療職が関与することが多い。ところが、同じ疾患に対する同じ抗がん剤治療なのに、主治医によって、使用する量が違っていたり、吐き気止めの種類や、投与方法が全く異なっていたり、という話はよく耳にする。原始的な病院では、主治医毎に「○○先生用指示」というのが用意され、それぞれの医師の流儀に精通した熟練看護師が病棟を仕切っている。しかし、このような不合理は、医療過誤の温床となる。確かに抗がん剤の投与量やスケジュールの間違いで、患者が死亡した事故の報告は多い。変更を必要とするような医学的な特殊事象がないかぎり、主治医にかかわらず、同じ手順で対応し、過誤の発生するチャンスを少なくする、業務を標準化するため、最近では、クリティカルパスの導入が進められている。がん医療では、グループ診療、チーム医療をもっと導入し、風通しのよい医療を行なうべきであろう。
グループ診療をささえるためのカンファレンス
私がレジデントとして研修を受けた頃の国立がんセンター病院内分泌グループは、乳がんを中心に、病態や治療にホルモンが関与する疾患の診断、治療を担当していた。阿部先生のほか、4名のスタッフ医師がおり、毎週火曜日の病棟回診では、この5人に私を加えた6名がナース・ステーションに集合し、約20名の入院患者一人づつについて、問題点、治療内容、今後の方針を担当医師が提示、とくに、個々の症状や徴候の背景となっている病態生理に関して、全員が共通の理解が得られるまで徹底的に議論が展開された。時には、口角泡を飛ばすような激しい議論になることもあった。印象に強く残っているのは、私が担当した38才の転移性乳がん患者、肺、肝臓、全身の骨に転移があり、寝たきりに近い状態であった。膝から下や口の周りが痺れる、という症状から始まり、次第に手もうまく動かなくなっていた。カンファレンスで、脳転移、抗がん剤の末梢神経障害、脊髄転移、ビタミン不足など、様々な鑑別診断が挙ったが、阿部先生から「カルシウム値はどうだ?」との指摘あり、測定すると低値であった。つまり「低カルシウム血症」、いわゆるテタニーの状態だったのである。骨転移を伴う乳がんでは、骨が破壊されカルシウムが溶け出し、血液中のカルシウムが高い値をしめす「高カルシウム血症」がしばしば見られる。それなのに、低カルシウム血症。理由がよくわからない。おそらく、ふつうの病院では、ここまでの鑑別はたどりつくだろう。そして、点滴の中身にカルシウムを追加して補正を試みることはするだろう。しかし、このチームでは、そこからの追求がすさまじかった。「なぜ、低カルシウム血症なのか?」、「造骨性骨転移(がんが骨に転移した結果、骨が溶けるのではなく、骨のカルシウム分がむしろ増加して骨が硬くなる転移形態、前立前癌の骨転移に多いが乳癌でもときに見られる)で、骨にカルシウムが取り込まれているのではないか。」、「いやいや、健常人の血清カルシウム値の調節には様々なホルモンやビタミンが関わっているからそう簡単には乱れないものだ。」、「じゃあ健常ではないとすれば、どこを調べればいいのか」、「ビタミンD、副甲状腺ホルモン、カルシトニン、血清アルブミンなどは調べる必要があるだろう」・・・。ということで、調べてみた結果、副甲状腺ホルモン(Parathyroid Hormone: PTH)が異常に低い、ということがわかった。PTHは、血清カルシウム値を上昇させる働きをもつホルモンだ。翌週のカンファレンスで、「低カルシウム血症の原因はPTH低値でした。」と発表したところ、「なぜPTHが低いのか?」、「いつから低くなったのか?」という話になり、「検査室に凍結保存してある過去の血清を使ってPTHを測定してみよう」ということになった。測定の結果、血清カルシウム値の低下と同じように、PTHが日を追って低下しているのがわかった。正常ではカルシウム値が低下すると、それを補正するためPTHは上昇する。どうやらPTHの分泌が悪いようだ、つまり、副甲状腺機能低下症ということになる。副甲状腺は、のどの甲状腺の裏側の四隅に張り付くようにある大豆ぐらいの大きさの内分泌腺だ。副甲状腺機能が低下する理由が、皆目検討がつかない。当時は、インターネットもない時代だったので、図書館司書のお姉さんに文献を検索してもらったが、そのような報告は全く見あたらなかった。結局、亡くなった後の病理解剖で、気管と甲状腺の間の隙間をはうように乳がん細胞が転移しており、副甲状腺が完全に破壊されていたのである。病棟カンファレンスでのこのような徹底的な討論で、ほぼ、病態の全容が解明できた。このとき、これが、内科の神髄なのだな、と感じた。とかく、がんの末期状態の患者では、どんなことがおきてもおかしくない、というような対応で、病態生理が解明されないことが多いように思う。腫瘍内科医は、まず、内科医である、というのは、こういうことなのだ。また、徹底した討論は、診療グループ内での問題解決や意志決定プロセスを熟成させ、共有化するには不可欠である。私が診療グループをまとめる立場になったときも、十分な議論を通じて、がん患者の病態生理を解明しようという姿勢を重視した。レジデント教育にはたいへん有意義だと高い評価を得た反面、そのような議論を、無意味、不毛、時間の無駄、と切り捨て、カンファレンスにも出席しない、出席しても腕を組んで居眠りをしている医師もいたが、グループ診療、チーム医療を、実践するためには、常日頃からの、担当者間の意思疎通のための徹底的な討論の積み重ねが不可欠である。
EBMを重視したがん医療
Evidence Based Medicineは、がん医療でも極めて大切な問題解決手法を提供してくれる。目の前にいる患者に対してどのような治療を行なうことがもっともよいことか。これは、すべての医療者が日々遭遇する命題であろう。EBMの手法では、この命題をまず、PECO形式の疑問文に作りかえるところから始まる。P(patient:どのような診断、病状の患者に?)、E(exposure:どのような治療を行なった場合?)、C(comparison:どんな治療を行なった場合と比べ?)、O(outcome:結果、効果はどうなのか?)。PECO文を作ることができれば解決すべき問題点が明確にできたことになる。さらに、PECO文に解答を出すように、過去の臨床研究や、基礎研究の論文を検索すればよい。抗がん剤治療の場合、治療の効果をすぐには実感できないことが多い。たとえば、初期治療での再発抑制効果を目指した治療をするにしても、治療を受けている患者一人一人にとっては、今、受けている治療の効果があるかないか検討がつかない。ただただ、副作用に苦しむばかりの日々を送るなかで、どの程度の治療効果が、科学的に確認されているか、という情報は、治療を継続する上での励みになるだろう。医師も、検証されたその効果を根拠として、つらい治療かも知れないけれどがんばりましょう、と患者を励ますことになる。がん医療においては、科学的な根拠を尊重する姿勢はとりわけ意味のあると思う。
街のがん医療をめざして
年間、約100万人の日本人が死亡するが、そのうち、35万人の死亡原因はがんである。がん医療に携わる外科医はたいへん多い。しかし、外科手術の限界も見えてきた昨今、放射線治療、薬物療法、などの必要性が急速に高まり、治療体系が大きく変容しようとしている。それなのに、手術以外の治療の担い手の育成が大幅に遅れているのが現状である。がん罹患者数の増加に加え、がんに関する情報は氾濫しており、民間療法や、不適切な免疫療法、リンパ球療法など、根拠の乏しい医療行為が横行している。一方、定評のある病院の外来は、患者であふれ、朝9時に受付をすませた初診患者の診療が夜7時から始まる病院もある。国立がんセンター中央病院では、最近、手術までの待機期間をホームーページで公表しているが、手術によっては「7.5ヶ月待ち」という信じられない数字をあげている。厚生労働省は、がん専門医の養成と適正配置を目指した均てん化策を講じようとしているが、その成果は、現状のニーズにはとても応えられない。いま、がん医療の専門家に求められていることは、日常生活、社会生活を送りながら、外来通院で抗がん剤治療を提供すること、および、氾濫する情報のなかから患者一人一人の医療状況に応じた適切な情報を取捨選択できるような援助をすることである。医師一人、薬剤師一人、看護師三人の最小単位から、都心の診療所に解説したオンコロジーセンターも1年が過ぎ、患者のニーズには、ある程度応えられていると思う。オンコロジーセンターがめざすところは街のがん治療である。辻々の交番のようにがん治療と情報提供ができるオンコロジーセンターがあれば、患者は都会のがん専門病院に行かなくても、安心と安全のがん医療をふるさとで享受することができるだろう。オンコロジーセンター二号店、三号店を目指したい。